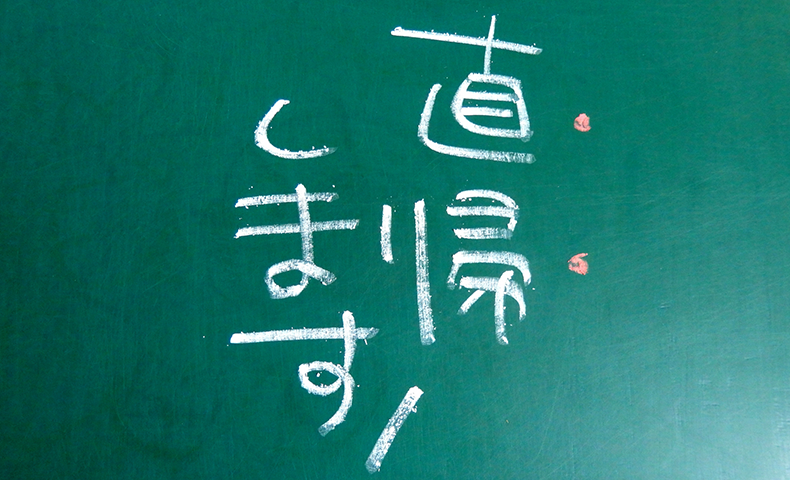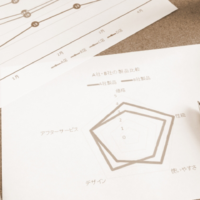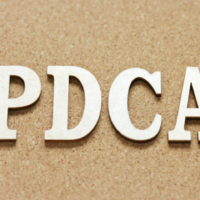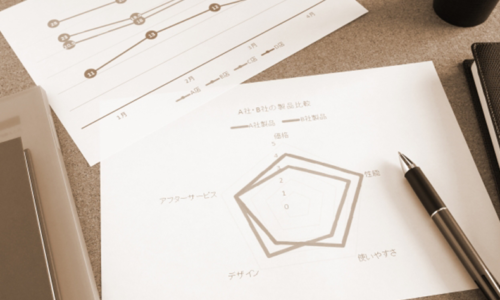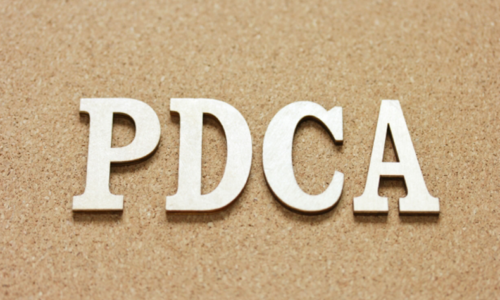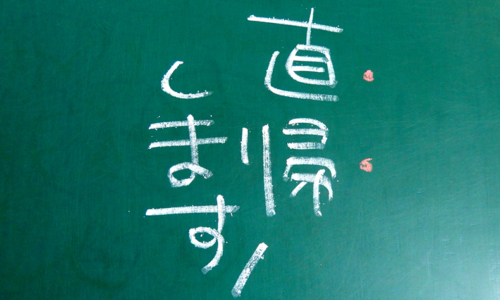Webサイトのアクセス解析において直帰率は重要な指標である。訪問してもらったユーザーが直ぐにサイトを去ってしまうことは、非常に勿体の無いことなので積極的に改善を行いたい。
直帰率とは
直帰率とは、Webサイトを訪れたセッション(訪問回数)のうち、直帰した割合を表した指標である。
初めてサイトに到達したページから、他のページにアクセスする事なくWebサイトを去ってしまう事だが、具体的に以下の様なアクションによって直帰している。
- ブラウザの戻るボタンを押した。
- ブラウザを閉じた。
- PCをシャットダウンした。
直帰率を正しく捉えるために見るべきデータ
前述で記載した通り、直帰率とはWebサイトの訪問回数(セッション)のうち、初めてサイトに到達したWebページ(ランディングページ)から直帰した割合である。よって、直帰率はランディングページに対してチェックを行うのが効果的。
Webサイトのページ数が多い場合は、比例して直帰率が高いページ数も多くなるため、訪問回数の多いページを優先から対応するとよいと思う。
直帰率が高くなる主な5つの原因
直帰率の原因に大きく影響するのは「訪問直前のページ」と「ランディングページ」の関係性である。この関係性を強くすることで、直帰率の改善と同時に滞在時間や回遊率の向上にも期待がもてる。以下、具体的なケースを記載する。
1.コンテンツが期待はずれだった
「訪問直前のページ」と「ランディングページ」の関係性とは、検索エンジン経由のアクセスであれば、Google等の検索結果に表示されるテキスト情報であり、メルマガ経由のアクセスであればテキストリンクに記載されている文章である。ユーザーは、それらの文章を読んだ上でその内容に期待してクリックするというアクションを起こしている。
クリックした先にあるコンテンツが期待値よりも低かった場合、ユーザーは他のWebサイトへ情報を求めて去ってしまう。
2.情報量が少なかった
検索エンジン経由のユーザーは、それなりに情報を検索して既に情報収集している可能性が高い。
あなたのサイトに訪れた時、既にあなたのサイトに掲載されている以上の情報量を持っている場合もある。
サイト訪問時に、「既に持っている情報だ」と判断されると、ユーザーはさらに新しい情報が掲載されるWebサイトを検索する。
3.ページが開かない
以下は、1993年にWEBサイトのユーザビリティ研究の第一人者であるヤコブ・ニールセンが行った、「応答時間に対する限界」についての有名な調査結果である。
Webサイトが開く時間と与える影響の関係性について
- 人の思考は、0.1秒までなら瞬時に表示されたと感じる。
- 人の思考は、1秒以内であれば途切れることなく流れる。
0.1秒~1秒以内であればユーザーは自由に操作できると感じている。 - 10秒以内であれば、人の思考は途切れながらも続いている。
ただし、限界に近い状態。他の作業へ意識が向きつつあり、いつ結果が返ってくるのか知らせる必要がある。
Webサイト開くのに、10秒必要な場合はほぼ怒って帰ってしまうだろう。
応答時間は、1秒までが理想的。2秒以内の維持が一つの指標となる。
4.サイトリニューアル直後は、URLの変更に注意
Webサイトをリニューアルした直後は、ページのURLが変更されている可能性が高い。
リニューアル後のサイト情報については、検索エンジンへ直ぐに反映されるわけではなく、完全に反映されるまでにある程度の時間が必要となる。
リニューアル前後のサイトURLが異なる場合、検索結果に対して表示されるページが404、もしくは全く別のページとなっている場合は必然的に直帰率は向上するので、こまめにチェックし301リダイレクト等の対処を行う必要がある。
5.意図しないリンク先へクリックしてしまった
最近多いのが、スマホアプリの画面上に表示されるディスプレイ広告を誤ってクリックしてしまい慌てて元のページに戻るケース。
もともとコンテンツに関連性が低く興味のないユーザーのアクセスである可能性が高いが、お金を払って広告を出稿している場合は、無駄に広告費が発生している可能性が高いためシビアにチェックしていきたい。
まとめ
直帰率をチェックする場合は、ランディングページのアクセス状況をチェックし、直帰率の高い傾向のあるページのうち、訪問数の多いページから優先して対策を行うようにしたい。
直帰率を上げる原因の多くは、流入元(サイトに訪問する直前のページ)とランディングページの関係性に潜んでいる可能性が高い。実際にユーザーの操作をシミュレーションしてみると、直帰する理由が手に取るようにわかることも少なくない。
直帰率の改善には1ページ毎の細かな対応が必要なケースも多いが、影響の大きいと思われるページをしっかりと見極めて対策していきたい。